放課後遊戯 見本 |
|||
| ―――――――――――――――――――――――――――――― | |||
■獄寺×綱吉「放課後遊戯」イントロ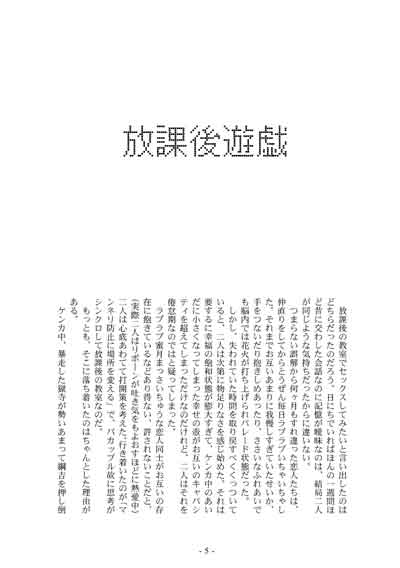
■1 隼人が気がついた時、部屋の中は真っ暗でカーテンの隙間から街灯の灯りがきらめいていた。 「っつ……う」 フローリングの床で眠っていたせいか身体の節々が軋む。同時に顎の辺りに覚えのない痛みを感じ手を当てると、腫れて熱を持っていた。 「……んだ…これ」 何故自分が床で眠っていたのか、殴られたかのような外傷を負っているのか、隼人は座り込んだまま記憶を辿る。 「っ十代目っ!」 思い出した瞬間に飛び上がった隼人は暗い部屋の中を見回し、舌打ちをして灯りをつける。視界がまぶしくて目を細めながらベッドの上や周辺を探してみるが、目当ての物は見つからない。 「まさかそのまま――」 姿ばかりか鞄や制服が見あたらないところを見るに、あるじは家に帰ったらしい。隼人は呆然と立ちつくし我に返ると、部屋着からジーンズとTシャツに着替えて財布を引っ掴み、部屋を飛び出した。 街灯のもと住宅街を走りながら、財布ではなく携帯電話を持ってくるべきだったととっさの判断が鈍っている己を罵る。 「……じゅうだい、めっ」 どれ程後悔しても最愛の人はいなくなってしまった。 隼人は涙でにじんだ視界を拭って走り続ける。 沢田家に着いた隼人はインターフォンを押し、反応がもらえる前に堪えきれなくなってノブに手をかける。普段から人の出入りが多い家のせいか鍵はかかっていなかった。 「おじゃましますっ」 断りながら玄関へ入ると、エプロン姿の奈々がちょうどリビングから姿を覗かせる。 「あらいらっしゃい獄寺君。ツナ、ワガママ言って獄寺君を困らせたりしてない? いつも仲良くしてくれてありがとうね」 「あああああのっ、お母様っ、十代目は――」 「ツナならお前の家で合宿中だろうが。寝ぼけてんのか」 いつの間に現れたのか、リボーンが奈々の足下で隼人を睨みつけていた。 「えっ、あっ、そ、そそそそのことでリボーンさんにちょっとお話がっ」 とっさに空気を読んだ隼人の判断は正解だったらしい。奈々は「じゃああとでお茶もってくからゆっくりしていってね」とにこやかに笑ってキッチンへ姿を消した。 リボーンに顎をしゃくられ指示される。隼人は促されるまま階段をあがった。 「アホ牛に聞いても要領を得ないから、一応ママンにはお前の家で合宿中と言っておいたが、ツナはどこに行ったんだ」 「……十代目は、多分……別世界に行かれたんだと思います。今日、ちょっと……ケンカになりまして……その時に、別世界に行くと仰ってたので……」 ローテーブルに仁王立ちしたリボーンを見る勇気などなく、隼人は床に正座してうなだれる。 「別世界に何の用がある。誰に、会うつもりなんだ」 リボーンの声の冷たさに、隼人は身をすくめた。読心術の使える家庭教師がわざわざ問うのは、誤魔化しを許す気はないと暗に言っているのだ。 「十代目は、昔会った大人のオレに会いに行くと……」 「お前は部下失格だ。守るべきボスをむざむざ危険な目に遭わせてどうする。異次元バズーカの特性上、以前と同じ場所に着くことはないと知ってるだろう。たまたま一度安全に戻れたからと言って、もう一度無事に帰ってくるか分からねえんだぞ」 隼人はいっそう俯き、身を縮める。 |
|||
| ―――――――――――――――――――――――――――――― | |||
| □20081028 up |
